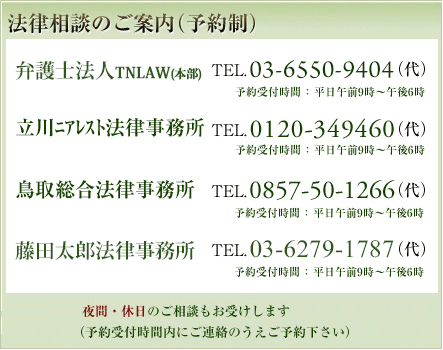当事務所の提供する個人のお客様向けの業務の一部をご案内します。
こちらでは、土地建物に関するトラブルの例についてご説明します。
1 住宅売買・建築
- (1)欠陥住宅
-
夢のマイホームを建てた(または買った)のに、その住宅に欠陥があったとしたら、本当にがっかりします。
法律上、建築の場合、注文者は、請負契約に関する担保責任規定(民法634条1項2項)に基づき、欠陥の修理や損害賠償を求めることができます。
また、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)や特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)では、新築住宅の基本構造部分に欠陥がある場合、請負人は、引渡しから10年間無償で修理すべき義務を負うとする規定を設けています(上の民法の規定では、建物の構造によって引渡しから5年または10年と制限されています。)。住宅瑕疵担保履行法は、建設業者に保険加入又は供託を義務付けており、基本構造部分の欠陥の修理を行う費用を確保できるようにしています。
また、売買の場合は、売買に関する瑕疵担保責任(民法570条)によって、売主に対して損害賠償請求ができます。
といっても、このような欠陥住宅に関するトラブルでは、そもそも「欠陥」(法律上は「瑕疵」といいます。)といえるのか,や、「害を受けたという「金額」について被告側から争われることが多く、またその判断は一般に思われている以上に難しいことが多いです。 裁判では、専門家の意見を聞く必要がある場合、専門委員制度や裁判所による鑑定を活用しながら、訴訟を進めていくことになります(その場合、鑑定等の費用やそれにかかる時間には相応のものが必要となります。)。
もっとも、いわば被害者的立場である注文者・買主にとって、時間もお金もかかる裁判は望むところではありません。
裁判を長期化させないためには、欠陥を発見した場合、できるだけ早い段階で(自分で修理をする前に)、状況を証拠化すること(写真、ビデオ等)、建築の知識のある方(急ぐ場合は近くの大工さんなどでもよいと思います。)に見てもらい、意見を書面にしてもらう,などの初期の措置があるとよいです。
よく「言えばわかるから。」「見てもらえば一目瞭然だから。」といって、状況を証拠化せず、請負人・売主との交渉を長い間続ける方がおられますが、後に裁判になったときに、当時の状況の証拠がないと建物を建てた時から問題があるのか後で問題が発生したのか分かりづらく、紛争の長期化・困難化は避けられないと思います。
また、欠陥を発見してからできるだけ早い段階で弁護士にご相談される方がよいことはもちろんです。
- (2)建設会社の倒産
-
土地・建物は一生の買い物と言われます。
しかし、新築工事を頼んだ建設会社が、まだ建築している間に倒産してしまったとしたら、どうなるでしょう。
建設会社は、従業員や下請業者にその後に支払う賃金などありませんから、その後の工事をそのまま続けてはくれません。一方で、注文者が建設会社に支払う代金は前払いであることが多いですが、倒産するような建設会社は、これを他への支払い等に充ててしまっていることが普通です。会社にはお金が残っていないので支払ったお金を返してもらうこともできません(お金が残っていても、破産手続による場合、配当を待たなくてはなりません)。
建てかかっている建物(建前)も、基本的にまだ所有権は建設会社にあることになり、注文者側で自由に処分することが制限されます。資材等にも、多くの場合、所有権留保等が付いており、他の業者によって引き揚げられてしまいます(または処分が禁じられます。)。 そのような状態で、注文者はいわば放り出されるわけです。
注文者は、その工事を続けたい場合にも、引き継いでくれる業者を探すのも一苦労です。というのは、倒産直前の会社がそれまできちんと工事を行ってくれているという保証はどこにもなく、引き継いだ業者は、完成させた後で欠陥があったと言われても困ってしまうからです。
また、苦労して引き継いで工事を行ってくれる業者を見つけたとしても、費用がかかります。当初の予定額から今まで支払った額を引いた金額で引き受けてくれる業者はまずいないと言っていいでしょう。
このように、建設会社が建築中に倒産すると、極めて大きな損害が発生します。
それを防ぐためには、まず予防措置として、当然のことですが、業者をよく選ぶことが必要です。大手の会社であれば、その決算書や株価等を見ることは比較的簡単ですので、注文前に念のため調べておくとよいと思います。また、財団法人住宅保証機構の住宅完成保証制度などを利用することも有益です。
しかし、これらをせずに新築工事を依頼し、建築中に建設会社が危ないという話を聞いたとしたら、それはすぐに弁護士に相談をするべきです。被害をその時点での最小限に食い止めることができるはずです。
2 賃貸
- (1)貸し手側から
-
- ア はじめに
-
土地・建物を賃貸する場合も、様々な法律上のトラブルの危険があります。
場面ごとにみてみましょう。
- イ 賃貸借契約
-
不動産業者を通して契約をするのであれば業者が契約書を作成してくれますが、個人で直接に借主に土地建物を賃貸する場合、自分で契約書を作成する必要があります。
契約書は、後日のトラブルの可能性を適切に見抜き、未然にそれを防ぐという観点から条項を設ける必要があります。市販の紋切り型の契約書の条項だけでは、貸し手の利益を守るためにとても十分とはいえません。一方で、契約書の条項は、法律に適合している必要があり、法律に反する条項が無効とされる場合も少なくありません。
これらのことから、実効的で有効な契約をするために、契約に先立って弁護士に契約書を見てもらうことはとても有益です。事前の多少の手間も、後日の大きなトラブルを回避するためには安いものです。
- ウ 賃料滞納
-
不動産を賃貸している場合、賃料の滞納は常にリスクとなります。
確実に賃料を得るためには、賃借人の資力をあらかじめ把握しておくことは当然ですが、生計を共にしない保証人を付けてもらうことも有益でしょう。
それでも賃料の支払いが遅れてきた場合、どのように対処すべきでしょうか。
遅れた分の賃料を請求することは、債権回収の一場面ですので、債権回収の項をご参照頂きたいと思いますが、ここでは、賃貸借に特有の問題について検討します。
まず、契約を解除できるか,ですが、賃貸借契約が信頼関係に基礎をおく継続的契約であることから、一般的には、単に1回遅れただけでは、信頼関係は破壊されず契約を解除することはできない,とされています。
どの程度、滞納されたら契約解除ができるかは、明確な基準がある訳ではありませんが、一般には少なくとも3か月程度の滞納は必要であろうと考えられているようです。逆にいえば、それ以前の滞納だけであれば、契約の解除はできず、解除を前提とする明渡し請求等もできないことになります。そうである以上、賃料の滞納により敷金でカバーしきれない損害が発生することを防ぐためには、滞納発生直後からきちんとした督促を文書で行い、「支払いをしなくても家主に催促なしで放っておかれたため信頼関係はいまだ破壊されていない」といった言い訳がされないように証拠を作っておく必要があります。
また、長期間賃料不払いが続いたからといって、無断立入り・荷物持出し・鍵の掛替え等の自力救済を行うことも、却って賃貸人に不法行為責任が発生しかねない危険な行為です。しかるべき手続き(訴訟→強制執行、又はそれに先立つ仮処分等)を踏む必要があるといえます。
近時、家賃を1か月でも滞納したら直ちに鍵の掛け替えを行う管理業者がいて、問題となっていましたが、それほどではないにしても、賃貸人の行為も十分注意をしないと違法のそしりを免れません。合法違法の判断も、一般の方では難しい面があるため、事前に弁護士に相談して頂きたいと思います。
- エ 立退き・明渡し
-
賃貸借契約を解除したのに出て行ってくれない,とか、そもそも賃貸借契約を結んでいないのに占拠されている,といった場合には、立退き・明渡しを求める必要があります。
任意の交渉でそれが実現しないときには、訴訟を提起し、判決を得ます。
そして、それでも立ち退かない場合には、強制執行を行うことになります。具体的には、裁判所の執行官により、不法占有者の占有を解いてもらうことになります。
もっとも、これを現実に行おうとする場合、相応の時間と費用がかかります。
すなわち、争点のない訴訟を行う場合であっても、判決を得るまでには数か月を要しますし、その後強制執行を行うにもそれから1~2か月はかかります。費用も、不動産によって大きく変ってきますが、訴訟と強制執行の手続にかかる費用だけで100万円以上に上ることも珍しくありません。このため、任意の交渉時にある程度の立退き料を支払って、訴訟・強制執行よりは、早期かつ安価に立退きを実現する方法もあります。
その選択はもちろん当事者次第でありますが、任意の交渉のときには、立退き料を支払ったのに出て行ってもらえない,という結果にならないよう、十分な段取りを行うことは必須です(この段取りのためにも、弁護士のアドバイスがあった方がよいと思います。)。
- (2)借り手側から
-
- ア はじめに
-
借り手側からみた賃貸借のトラブルも、基本的には貸し手側からみたそれの裏返しです。
もっとも、借り手側は、まさに住居として使用しているケースが多く、生活への密着度からすればより重要といえるかもしれません。
- イ 賃料滞納
-
上でみたとおり、賃料の滞納は単に1か月遅れた程度では契約は解除されにくいといえます。
しかし、これが頻繁に繰り返されたり、他に賃貸人との信頼関係を破壊する行為を行っていたりする場合等は、契約の解除に至ってしまうこともあり得ます。
例えば、収入が減る等して賃料の支払いが滞ることとなった場合、まず賃貸人に誠実な態度で賃料支払いを猶予してもらえるよう交渉を行うことが有効だと思います。
一方で、減った収入が回復する見込みがない場合、適宜、生活保護や社会福祉協議会の緊急融資などの方法で、生活費を確保するべきだと思います。この点は債務整理の項もご参照ください。
- ウ 敷金
-
「敷引特約で金額が引かれたがその特約は有効なのか。」「思ったより少ない金額しか返してもらえなかった。」
敷金は、従前からトラブルになりやすい問題でした。
敷引特約については、近時、裁判例が蓄積されつつあるところで、名古屋簡裁判決平成21年6月4日のように消費者契約法に反し無効とする判断が多いようです。特約が無効となれば、一律に差し引かれていた敷金の返還を受けられることになりますので、「契約書に書いてあるから。」とか「契約時に説明を受けたから。」という単純な理由で諦めないで頂きたいと思います。
また、敷金の金額が考えていたより少額だった場合は、差し引かれた金額の内訳の明示を求め、その内容が妥当かを検討するべきです。不要な工事代金まで含まれている場合、その分の金額について返還請求ができます。工事の要不要を明らかにするためには、退出時の部屋の状況を写真に撮って証拠化しておくこと等が有効です。
もっとも、敷金返還請求は、請求金額が多くて数十万円に留まることが多く、弁護士費用に見合わないという懸念があるかと思います。当事務所では、できる限り依頼を行いやすい弁護士費用を提示するよう心掛けておりますので、まずはご相談頂ければと思います。
- エ 更新料
-
更新料問題も、敷金と同様、近時裁判例が多く出ているところです。
もっとも、大阪高裁判決平成21年8月27日は更新料特約を無効とした(返還請求を認めた)のに対し、同じ大阪高裁平成21年10月29日はこれを有効としており(返還請求を棄却した)、事例ごとに判断は分かれているといえます。
返還請求は、容易でない側面がありますが、請求を行うことが意味がないとはいえません。内容のよく分からない不当な更新料は返還されるべきですので、ご依頼頂ければ当事務所では真摯に取り組みたい考えです。
3 近隣紛争
- (1)はじめに
-
隣の家やご近所とのトラブルは非常にストレスが溜まります。
問題を大きくすることに不安を感じる方は非常に多いのですが、放置しておけば、ますます問題は大きくなってしまいます。
近隣紛争は、適切な時期に適切な方法で対処する必要がある極めて難しい問題といえます。
- (2)騒音、振動
-
近隣紛争のうち、もっとも多いトラブルが騒音や振動です。
法律上は、「受忍限度」という基準を用いて、それを超える場合に差止めや損害賠償を認めています。
もっとも、「受忍限度」がどの程度のものかは容易に分からず、またそれ以下だった場合に何もできないとすることは相当とはいえません。
例えば、民事調停やADR等の方法で、第三者を交えて、冷静に話し合う場を設けることも非常に有益と考えます。
- (3)境界
-
近隣紛争では、境界に関する争いも深刻なものとなりがちです。
特に歴史が古い件は、当事者が感情的になりやすく、なかなか和解に至りにくいものです。この種の紛争の場合、できる限り多くの資料を収集することで、合理的な結論に至る可能性が高まります。
境界に関する紛争を解決する方法としては、境界確定訴訟、筆界特定制度、境界ADR等があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。どの手続を利用するかによって、解決までに要する時間、費用、労力が異なりますので、その選択は重要です。当事務所では、依頼者様に状況に応じた最も適切な解決方法を提案致します。
土地建物のトラブルについて、当事務所にご相談されたい方は「ご相談の流れ」へどうぞ。
4 保全処分
上のような訴訟を行っている間に、相手方が重要な財産を処分してしまったり、費消してしまったりしたら、どうなるでしょうか。その後にせっかく勝訴判決を得ても、強制執行ができず支払いを受けられないという結論になってしまいます。
法律上、そのような事態を防止するために、訴訟に先立って相手方がその財産の処分を行うことができなくなるよう命令を発してもらうことができます。
あくまで判決前の「仮の」処分であることから、相応の額の保証金を裁判所に納付する必要がありますが、それによって将来的に支払いが確保されるのであれば極めて有用です。
ただし、そのような命令を発してもらうためには、請求している債権が一応存在すること(被保全権利の存在)や、今財産を保全しなければ将来支払いを受けられなくなる恐れがあること(保全の必要性)の疎明(裁判所が一応確からしいと思う程度に証明すること)が必要です。
5 強制執行
訴訟で勝って判決を得ても、相手方が支払いをしてくれない場合、強制的に相手方の財産から支払いを受ける必要があります。
具体的には、相手方の持っている財産(不動産、動産、債権)を競売等でお金に換えてもらったうえで、その支払いを受けるという手続になります。
欠点としては、不動産の強制競売の場合、申立費用が高いこと、競売にかかる時間がかかること(通常半年以上)、抵当権等が設定されている場合には一般債権は劣後することが挙げられます。また、動産の場合、相応に高価な動産が存在する必要があること、相手方の動産の所有状況が当方からは分かりにくいことが挙げられます。債権についても、預金債権であれば金融機関の支店名まで特定する必要があることや、給与債権であれば勤務先が分かっていること、差押えのできない債権があることが挙げられます。
また、全体に共通することですが、財産を全くもっていない相手方に対しては強制執行を行うこともできず、判決が「絵に描いた餅」になってしまうという危険もあります。
しかし、自力救済が禁じられる現行法下において、強制執行が任意に支払いを行わない相手方から強制的に支払いを受ける最終手段であることは変わりありません。
なお、財産を隠す相手方に対しては、(効果の程度はともかく)財産開示命令という制度もあります。
6 民事調停
民事調停は、裁判所で行われる手続ですが、訴訟とは違って必ずしも法律に縛られることなく、裁判官1人と調停委員2人による調停委員会が当事者の間に入って話合いを行うというものです。通常、調停委員がいる部屋に当事者が順番(交互)に入り、それぞれの話を聞いてもらいながら、相手方との合意を目指す方式がとられます。
直接相手方と対面しないため、双方が感情的にならずに話し合うことが可能となり、また、中立の第三者(調停委員)の意見も聞きながら妥協点を見つけることができるため、結論には一定の合理性が期待できます。
双方が合意に達すれば、裁判所により判決と同じ効力を持つ調停調書が作られて、紛争は解決します。しかし、回数を重ねても合意に達しない場合には、調停は不成立となり、紛争は解決しませんので、民事調停を申し立てる場合には、最終的に相手方と妥協の余地があるかを事前に十分検討することが必要です。
7 ADR
近時、裁判所以外の機関による紛争解決手続としてADR(Alternative Dispute Resolution 裁判外紛争解決手続)も注目されています。これは従来の裁判所の手続の、時間がかかる、費用がかかる、手続が難しい等の欠点を克服すべく、もっと柔軟な利用しやすい制度として登場したものです。
運営主体は様々あり、得意とする分野もそれぞれ異なるので、どのように使うかは慎重に検討する必要がありますが、専門性の高い紛争を迅速に解決するためには有用な制度といえます。
土地建物のトラブルについて、当事務所にご相談されたい方は「ご相談の流れ」へどうぞ。